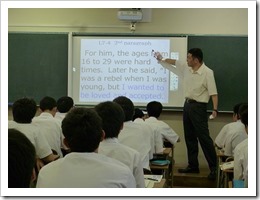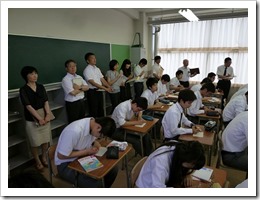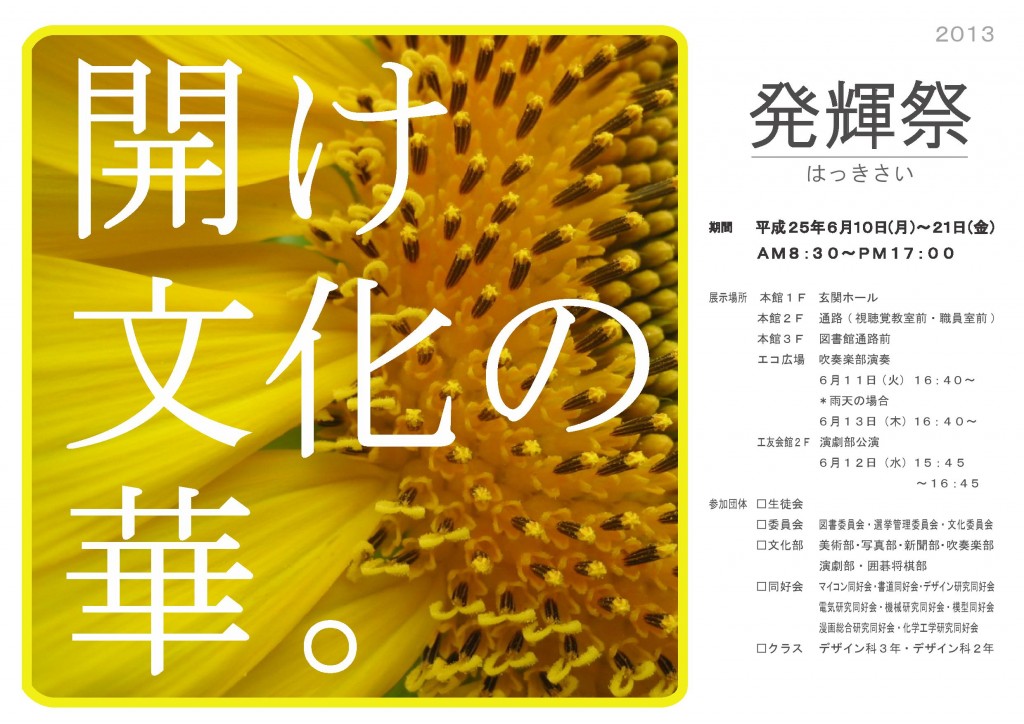6月8日(土)、岡山県高校総体ラグビーフットボール競技の7人制の部が、美作ラグビー・サッカー場で行われました。
7人制ラグビーは、通称「セブンズ」と呼ばれ、スピードとパスワークを重視したラグビーフットボールです。2016年のリオデジャネイロオリンピックで正式種目に採用されました。試合時間は7分ハーフと短いですが、15人制の試合と同じ広さで行うため、持久力とランニングスキルが勝敗を分けます。来年からインターハイ種目となり、全国大会も行われます。
1回戦 岡工 43-0 高松農業高校
試合開始から、積極的にボールを繋ぎ、連続トライを奪いました。選手たちは互いに声を掛け合い、グランドを縦横無尽に走り、楽しんでラグビーができていました。



2回戦 岡工 7-34 金光学園高校
試合開始早々、何でもないミスからトライを許すと、その後精神的に立ち直れず、初戦とは別人のような、消極的なプレーが目立つ試合となりました。



残念ですが、このチームにはメンタルの強さが足りないことを、改めて認識させられる結果となりました。
岡工ラグビー部はチーム全員でこの敗戦を生かし、技術と精神を磨き、ひと回りもふた回りも成長したいと思います。そして、暖かい応援をしてくださる保護者の皆様に良い報告ができるよう練習してまいりますので、これからもどうかよろしくお願いいたします。