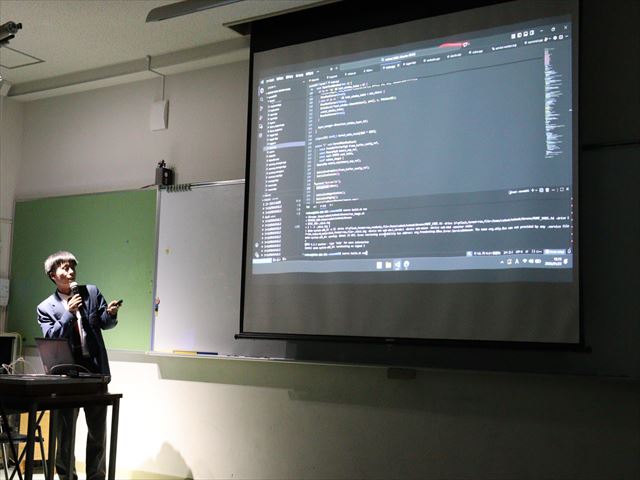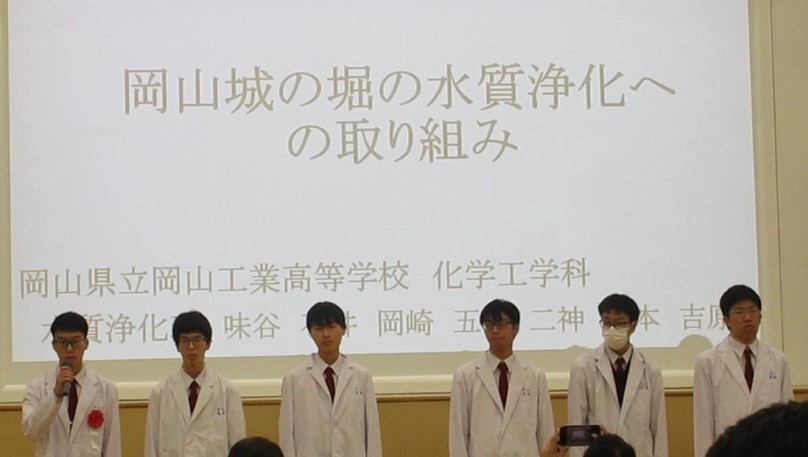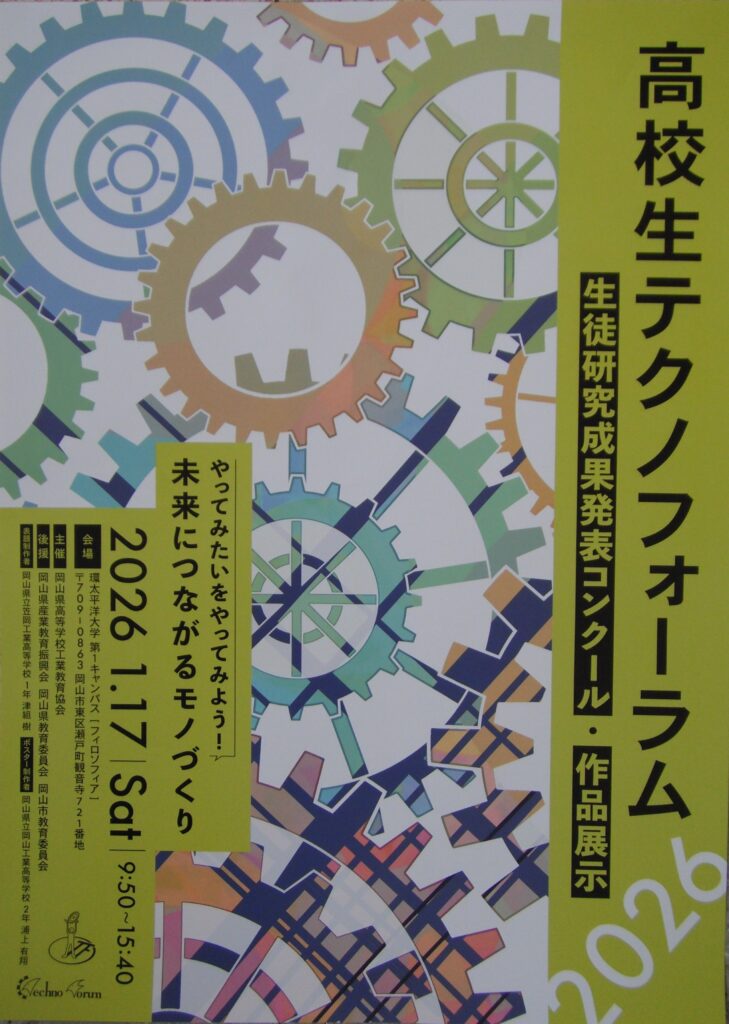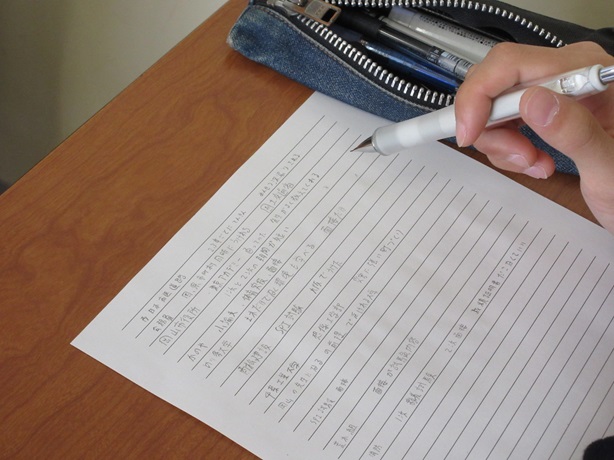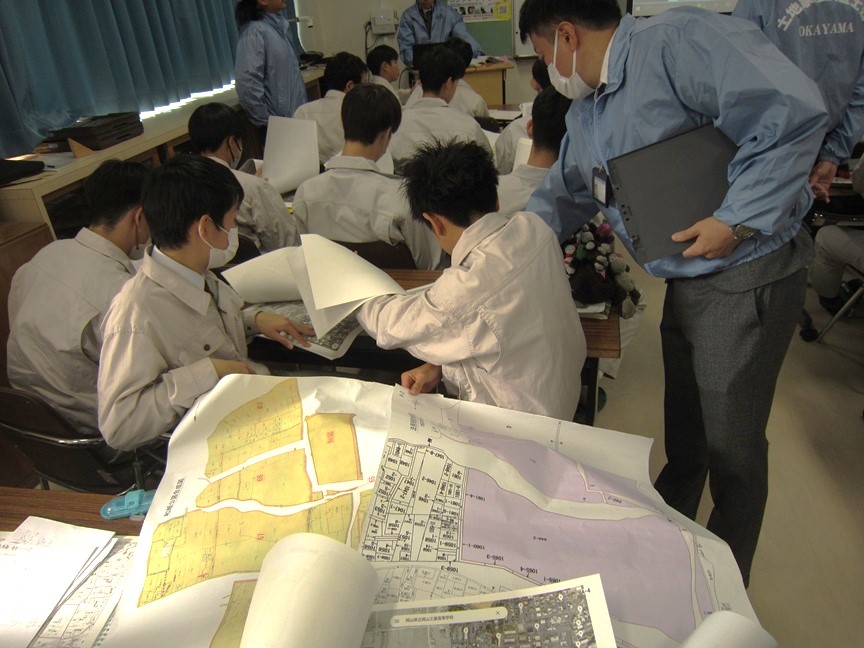1/24(土)京山公民館にて「京山ESD・SDGsフェスティバル」が行われ、化学工学科(化学工学研究同好会)と建築科(建築研究同好会)がものづくり教室を行いました。
化学工学研究同好会はプラスチックの熱可塑性などの現象を利用した化学実験「オリジナルプラバン」、「人工カプセル」、「スライム」、「アルコールロケット」を行い、建築研究同好会は端材と半田ごてを用いた「キーホルダー作り」を行いました。
予想以上の人が来られて大変でしたが、とても思い出に残る楽しい時間を過ごすことができました。訪れてくださった皆様、関係の皆様方、ありがとうございました。