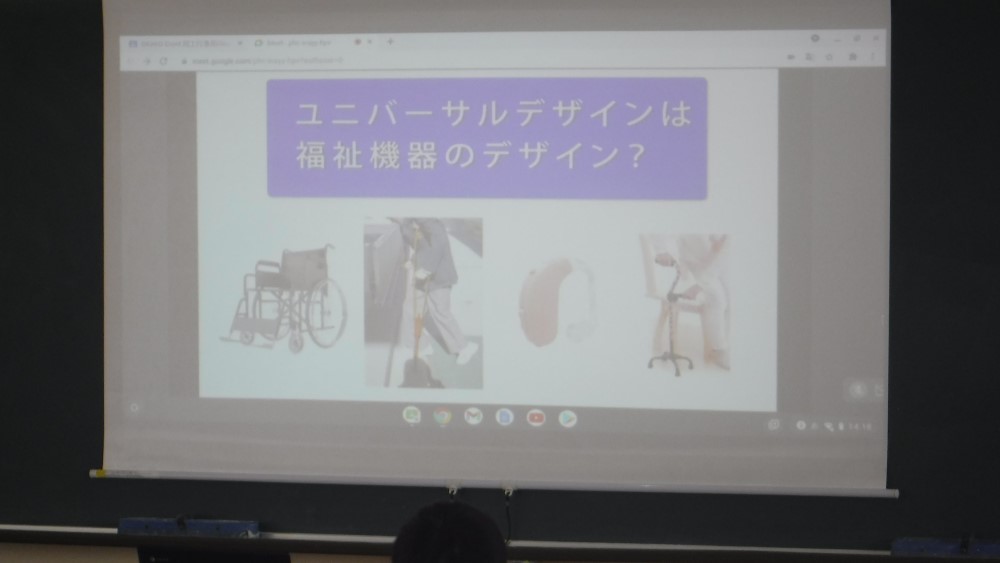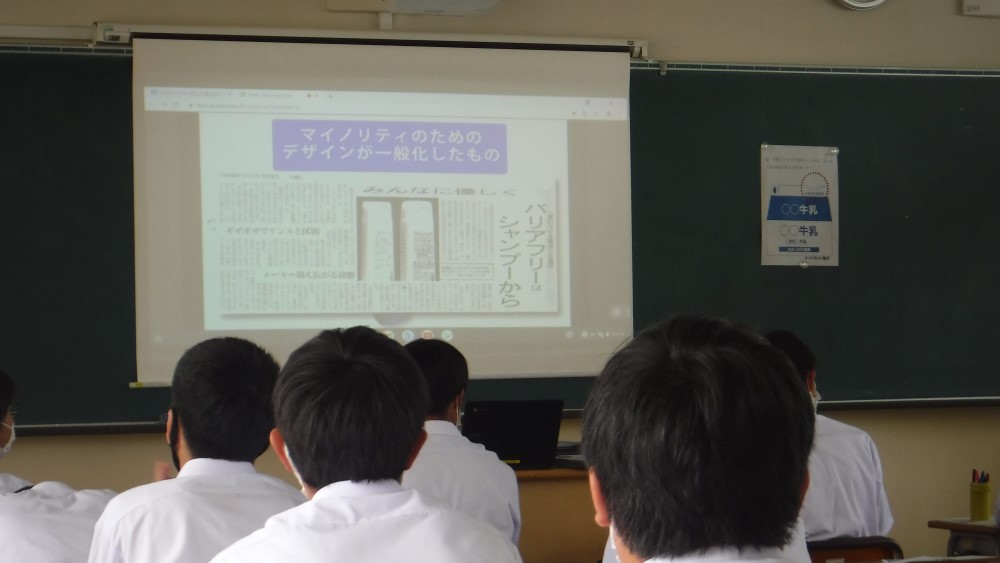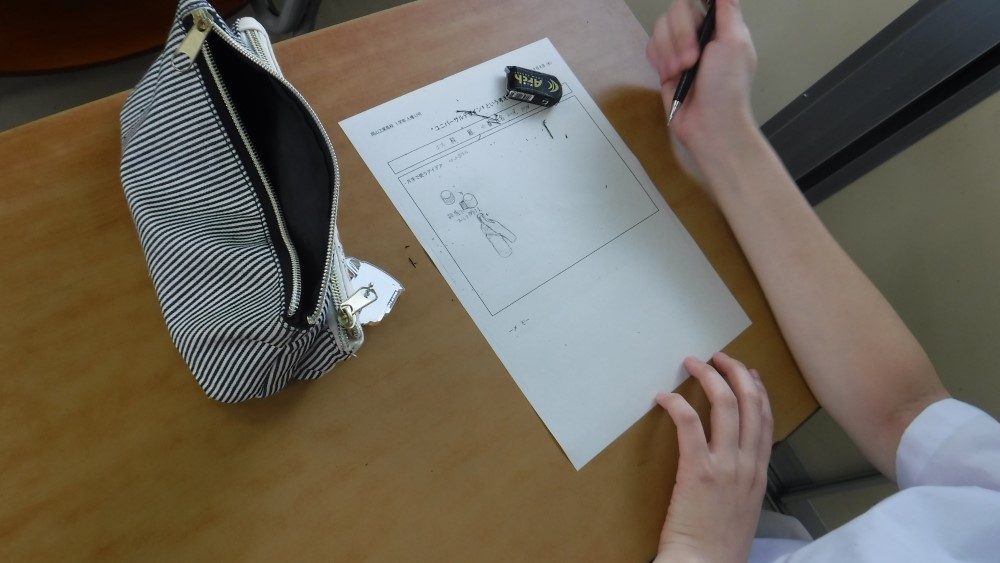1年生対象の人権教育LHRは、「ユニバーサルデザインという考え方」という演題で、本校デザイン科の山形先生に講演をしていただきました。
1950年代にデンマークの行政官であるエリック・バンク・ミケルセンが「ノーマライゼーション」の概念を提唱しました。「障がいのある人は、障がいのある人だけが暮らしやすい施設隔離すべきなのか。それでは収容所と同じではないか。障がいを持っていても均等に当たり前に生活できる社会こそがノーマルな社会である」と唱えました。
1980年代にはアメリカの建築家・工業デザイナーであるロナルド・メイスが「ユニバーサルデザイン」の概念を提唱しました。「標準的な設備・製品と障害のある人が使う設備・製品を区別して作るのではなく、はじめから多様な人が使える設備・製品のデザインを考えるべきである」と唱えました。
現在は、マイノリティのために考えられたデザインが一般化している事例があります。牛乳パックの凹みやシャンプーボトルのギザギザなど、たくさんの事例があります。今日の講演を踏まえて、日常の製品の中にどのような配慮がなされているか見つけてみようと考えてくれた生徒がいました。
生徒の振り返りでは、「ユニバーサルデザインは、不自由な人のためにあるデザインだと思っていたが、誰もが使いやすいデザインであることを知りました。街に出てみていろんなところにきっとユニバーサルデザインがあるはずなので探してみようと思いました。」「世の中にはまだまだ実は使いやすくない製品や道具があると思うので、これから自分の力でみんなが使いやすい物を、いろいろな視点を持って考えていきたいと思った。」「日常にあるユニバーサルデザインの製品が誕生する話を調べてみようと思う。将来自分が「ものづくり」をする際に、すべての人に配慮した製品を思考・製作できる人材になりたいと思った」など、今回の勉強が将来の「ものづくり」への力に繋がってくれました。
ユニバーサルデザインとは、これから「ものづくり」に携わるすべての人に必要な考え方です。将来おこなう「ものづくり」は、誰かに使ってもらう、誰かに見てもらう、誰かのために思考・製作することになると思います。自分だけの価値観や考え方を問い直すことが、「ものづくり」をおこなう上でも大切であることを伝えました。
この講演で学んだことを活かすために、「片手で空けるペットボトルのデザインを考えよう」という課題を出しました。生徒達がどのようなアイデアを出してくれるか楽しみにしています。
岡山工業高等学校 BLOG
最新情報をお届けします