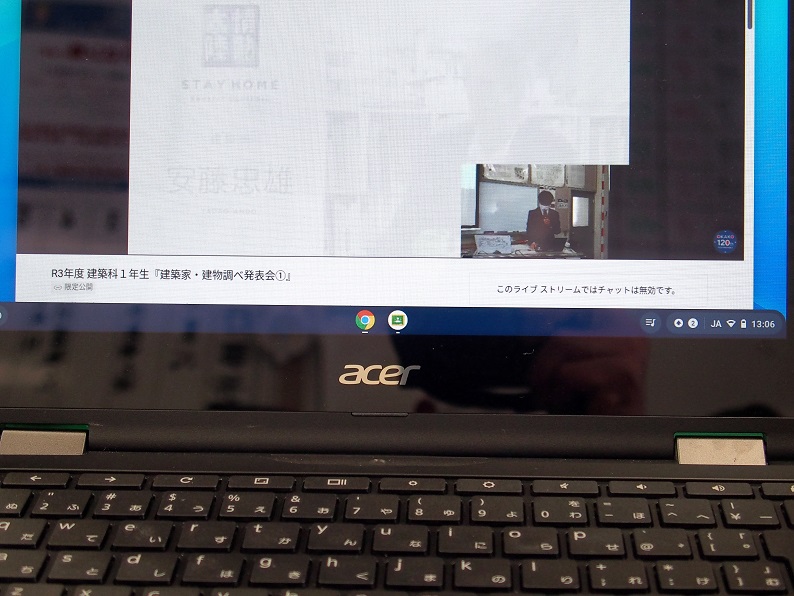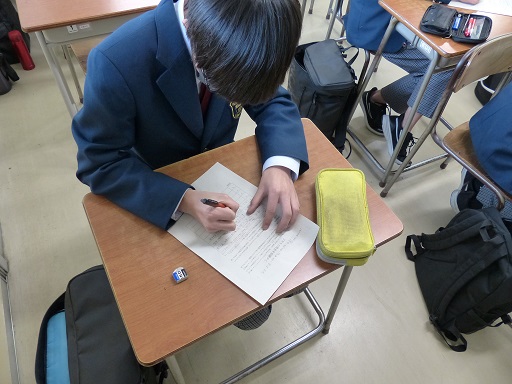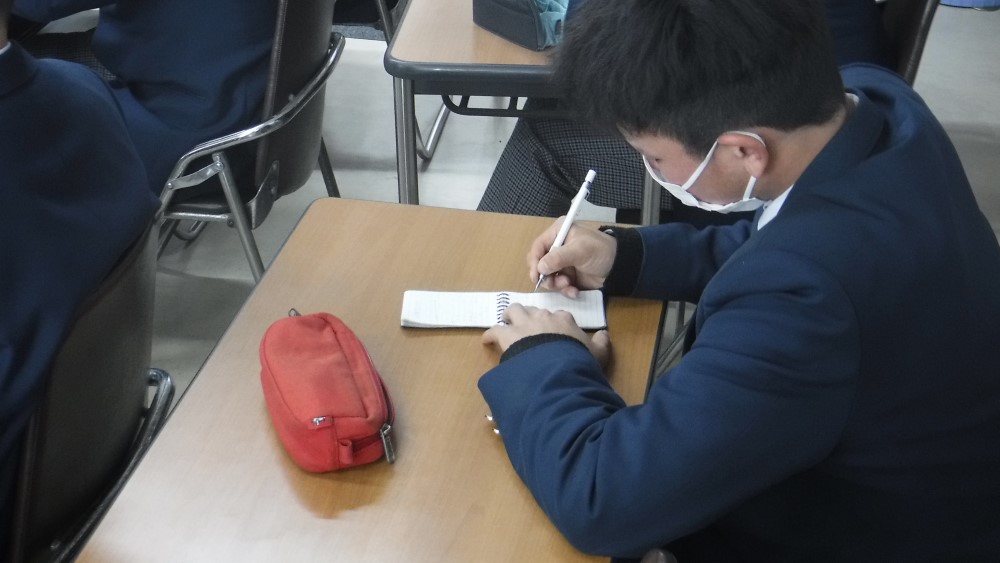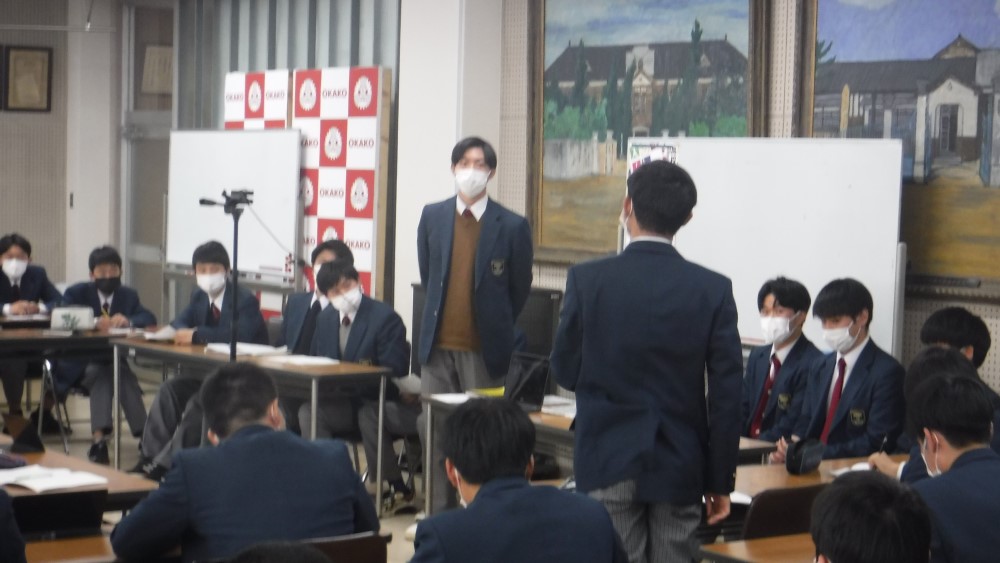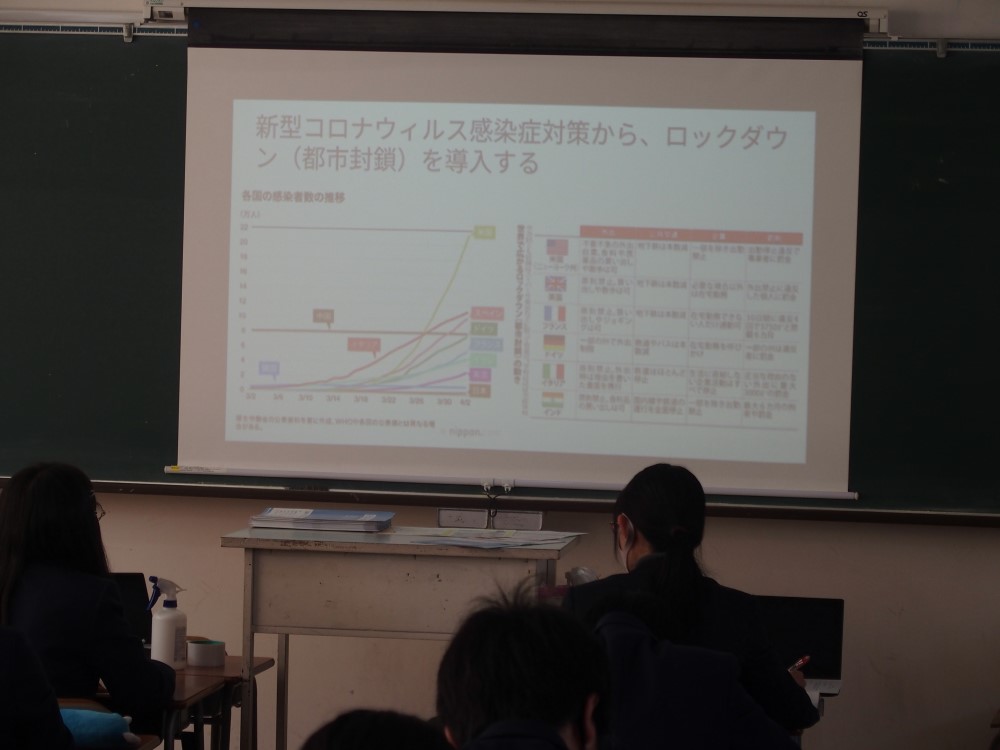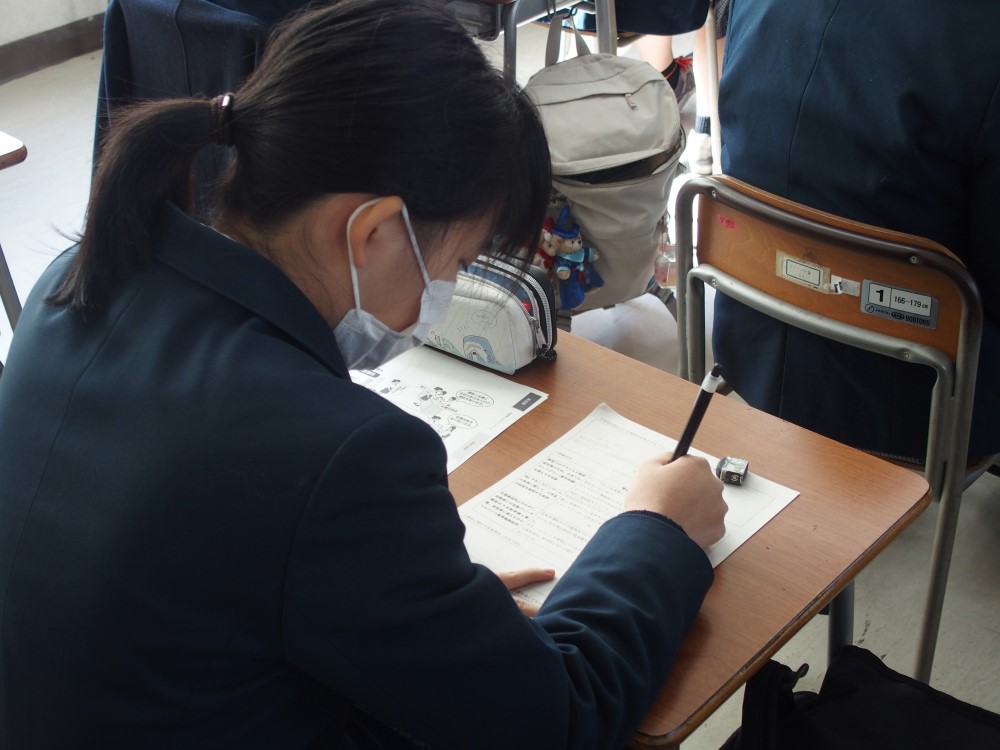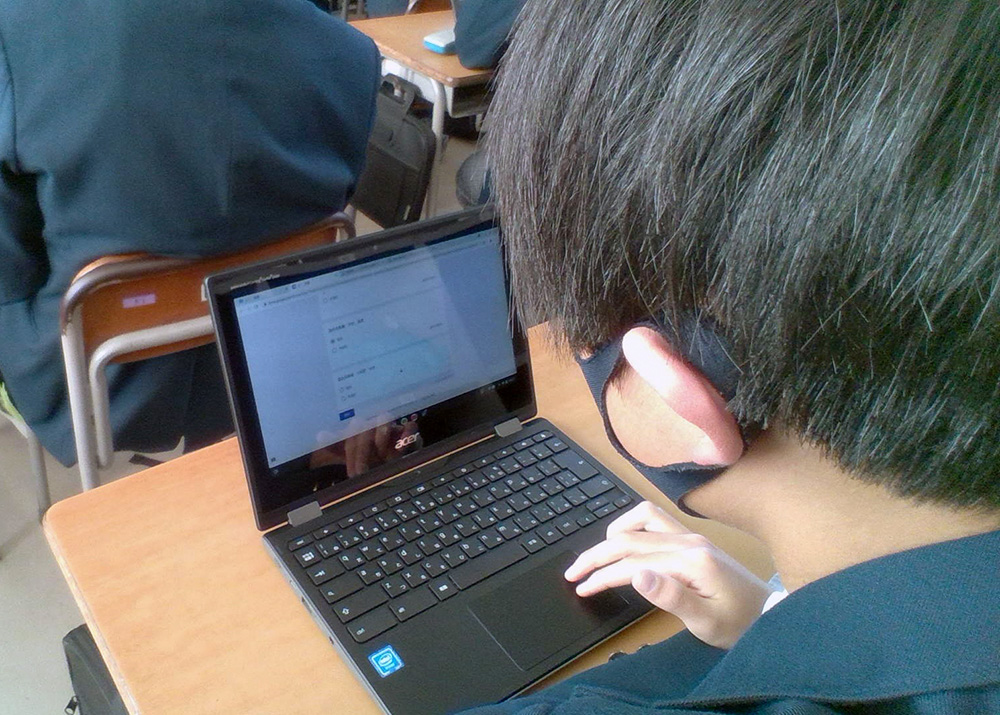入選 デザイン科2年 千田 見欧さん
「固定された価値観~『告白』を読んで」
デザイン科2年 野口 智尋さん
「漁港の肉子ちゃんを読んで」
佳作 デザイン科2年 入野谷 葉琉さん
「生活を見つめ直す~『そして生活は続く』を読んで」
夏休みの課題で1、2年生に読書感想文を提出してもらいました。300編あまりの中から、学校を代表して12編を県のコンクールに応募したところ、3編が入賞しました!! 県全体では329編の応募があり、その中で選ばれたのですから、たいへん価値のある受賞だといえます。なお、実業系の高校の中で岡工の応募数はトップであり、これも素晴らしいことでしょう。
受賞した3名に読書についてお話を聞きましたので、紹介します。
千田さん:
「本を読むと、作者の人間性や遊び心などが見えてきて楽しいです。作者さんと実際におしゃべりできたら、どんなことを言うのだろう、作品への情熱はどのくらいなんだろう・・・などと考えながら読むのもワクワクします。本を読み始めると、周りの音も聞こえなくなるような感覚がして、他のことも忘れてしまうくらい物語の世界に入り込んでしまいます。」
野口さん:
「小学校の図書室がとても居心地が良くて、面白かった本を何度も借りて繰り返し読んだり、ジャンルを問わず手当たり次第に読んだりしていました。中学生の頃に読んだ手塚治虫の『火の鳥』は、予想できない展開や見事な伏線の回収に、本を持つ手が震えたのを覚えています。最近は朝井リョウさんの『死にがいを求めて生きているの』がおもしろかったです。」
入野谷さん:
「小さい頃から読書が好きで、絵本や図鑑をよく読んでいました。新しいことを知ったり、素敵な世界観に触れたりするたびにワクワクした体験が、読書の習慣につながっているんだろうと思います。文章という表現は、他のどんな表現よりも想像を膨らますことができる余白があり、文字で展開される情景を自分の好きな形で想像できるのが、読書の魅力ではないでしょうか。」