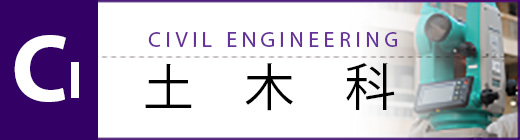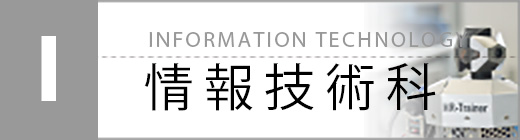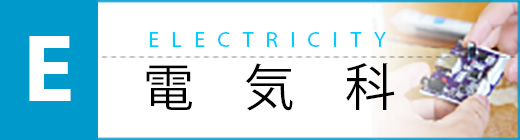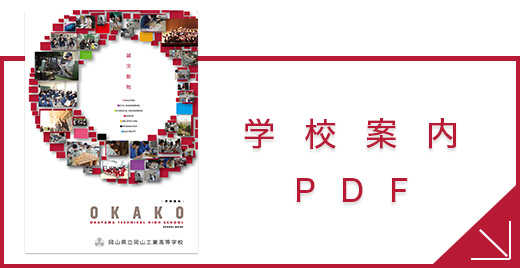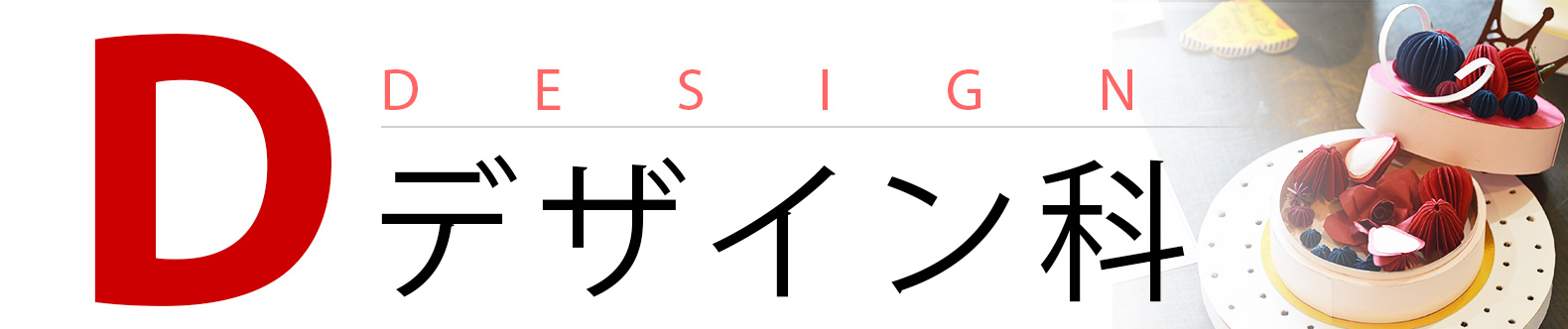
デザイン科 授業紹介
1年生
- 実習
-
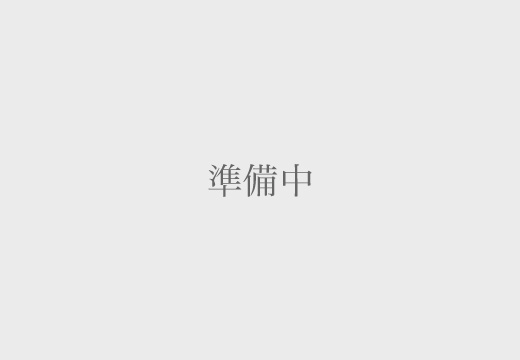
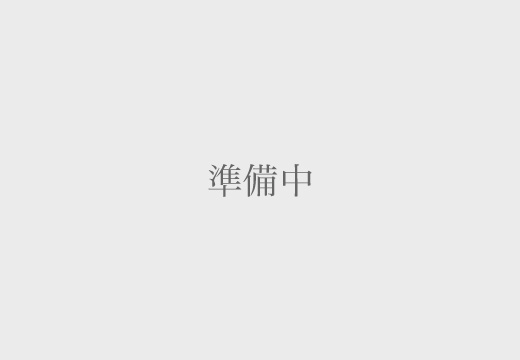
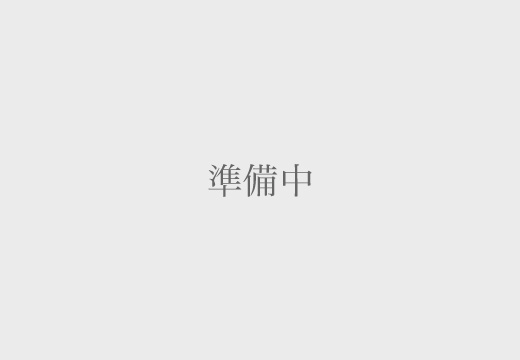 実習は1年時5単位(週5時間)。デザインの3つの分野(ビジュアルデザイン・プロダクトデザイン・環境デザイン)について、作品制作を通じて実践的に学習していきます。1年生は、デザインサーベイ(調査)やアイデアの出し方、道具の使い方など基礎から学び、平面構成や紙や粘土による立体造形などハンドワークを中心に作品を制作します。例えば、毎年恒例の課題の一つに池田動物園の園内マップの作成があります。岡工から徒歩数分のところにある池田動物園に実際に行き、自分の足で園内を散策します(デザインサーベイ)。自分の目で見て調査した内容を学校に帰って整理し、園内マップのアイデアスケッチをします。誰が見てもわかりやすく、行ってみたくなるようなデザインにするためには、いくつもアイデアスケッチを重ね、1つの案に絞っていかなくてはいけません。見る人の立場に立って考え、1つの作品をていねいに仕上げていく過程で、デザインの一連のプロセスを学ぶことができます。
実習は1年時5単位(週5時間)。デザインの3つの分野(ビジュアルデザイン・プロダクトデザイン・環境デザイン)について、作品制作を通じて実践的に学習していきます。1年生は、デザインサーベイ(調査)やアイデアの出し方、道具の使い方など基礎から学び、平面構成や紙や粘土による立体造形などハンドワークを中心に作品を制作します。例えば、毎年恒例の課題の一つに池田動物園の園内マップの作成があります。岡工から徒歩数分のところにある池田動物園に実際に行き、自分の足で園内を散策します(デザインサーベイ)。自分の目で見て調査した内容を学校に帰って整理し、園内マップのアイデアスケッチをします。誰が見てもわかりやすく、行ってみたくなるようなデザインにするためには、いくつもアイデアスケッチを重ね、1つの案に絞っていかなくてはいけません。見る人の立場に立って考え、1つの作品をていねいに仕上げていく過程で、デザインの一連のプロセスを学ぶことができます。
- 工業技術基礎-デッサンコース
-
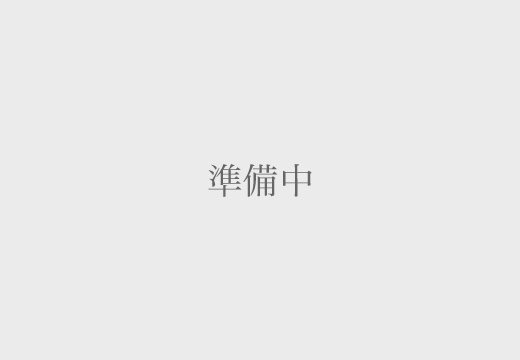
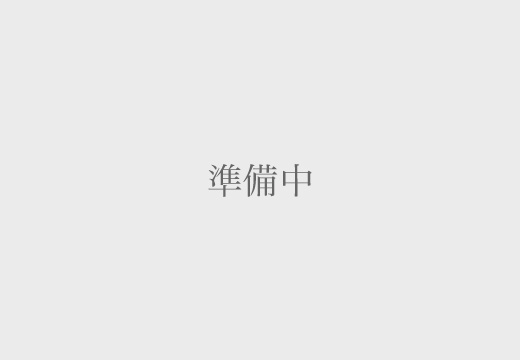
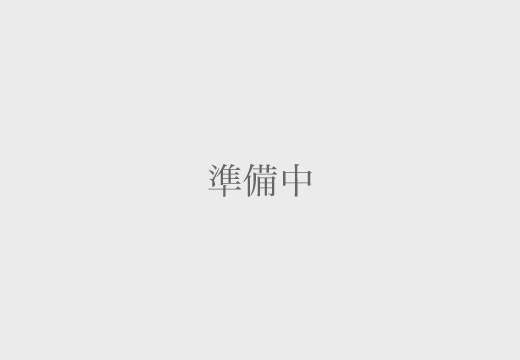 デッサンは、モチーフを「観察」し「表現」する、デザインやものづくりの基礎トレーニングです。形を正確にとらえ、画面の中にバランスよく配置し、陰影や材質感などを鉛筆の濃淡で表現していきます。
デッサンは、モチーフを「観察」し「表現」する、デザインやものづくりの基礎トレーニングです。形を正確にとらえ、画面の中にバランスよく配置し、陰影や材質感などを鉛筆の濃淡で表現していきます。
- 工業技術基礎-木工コース
-
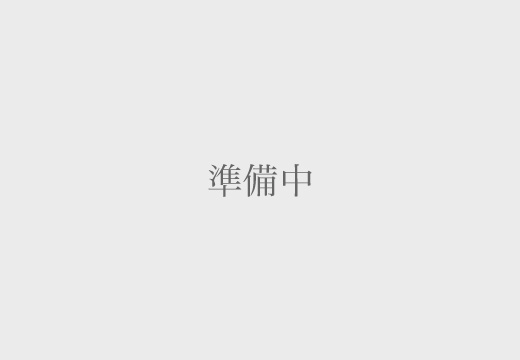
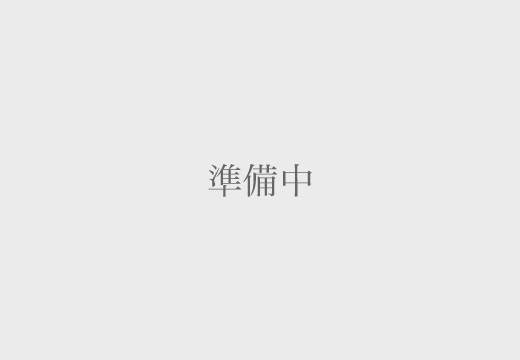
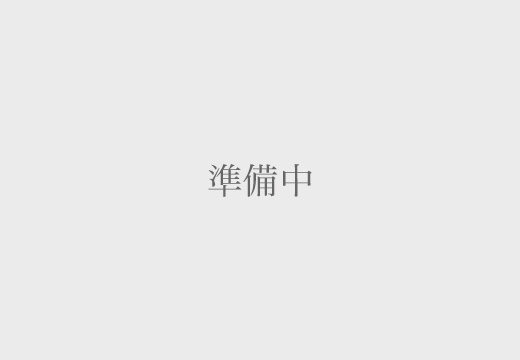 木材の基礎知識を学び、糸のこ盤、ボール盤、ベルトサンダーなどの機械を使って、カムで動く木のおもちゃを制作します。「カム」というのは、自動車のエンジンの中にも使われている機械の動きを変換する機構です。ハンドルを回すと、本体下部のカムが回転運動を往復運動に変換し上部の可動部分が動きます。
木材の基礎知識を学び、糸のこ盤、ボール盤、ベルトサンダーなどの機械を使って、カムで動く木のおもちゃを制作します。「カム」というのは、自動車のエンジンの中にも使われている機械の動きを変換する機構です。ハンドルを回すと、本体下部のカムが回転運動を往復運動に変換し上部の可動部分が動きます。 - 工業技術基礎-パソコンコース
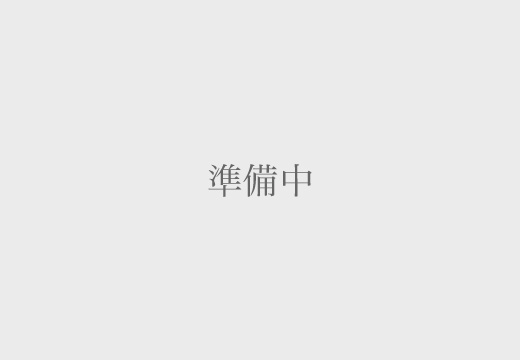

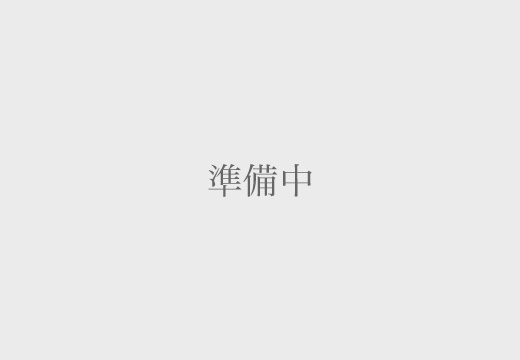 Adobe社 llustrator(イラストレータ)、Photoshop(フォトショップ)など、実際のデザインの現場で使われているソフトを使い、DTP(デスクトップパブリッシング)の基礎を学びます
Adobe社 llustrator(イラストレータ)、Photoshop(フォトショップ)など、実際のデザインの現場で使われているソフトを使い、DTP(デスクトップパブリッシング)の基礎を学びます- 工業技術基礎-シルク印刷コース
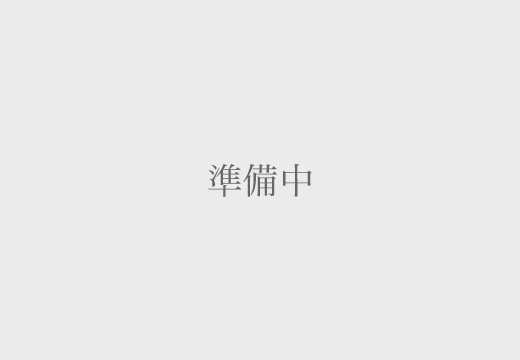
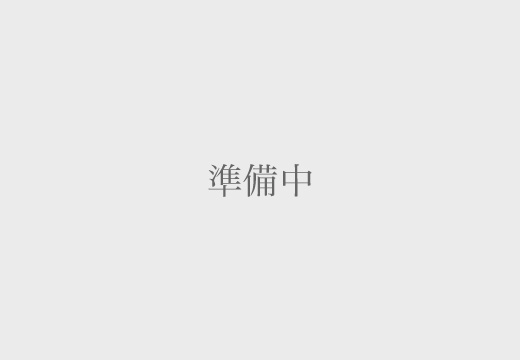
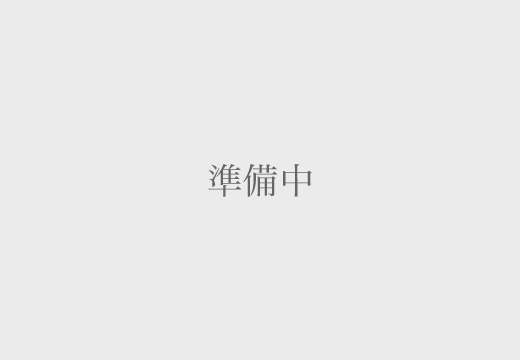 シルクスクリーンは孔版印刷(こうはんいんさつ)といわれる印刷技法の一つです。孔版の「孔」は穴という意味で、文字通り版に開いた穴をインクが通って紙や布に転写します。このコースでは、紗張り(版の枠にシルクを張る作業)から製版、インクづくり、刷り作業までのシルクスクリーン印刷の一連の作業を体験します。
シルクスクリーンは孔版印刷(こうはんいんさつ)といわれる印刷技法の一つです。孔版の「孔」は穴という意味で、文字通り版に開いた穴をインクが通って紙や布に転写します。このコースでは、紗張り(版の枠にシルクを張る作業)から製版、インクづくり、刷り作業までのシルクスクリーン印刷の一連の作業を体験します。
工業技術基礎(工業技術基礎は、工業系の学科で学ぶ生徒が全員履修する科目です。デザイン科では、1年時に3単位(週3時間)で、クラスを10名ずつの4班に分け、4つの学習内容を順番にローテーションしながら学んでいきます。
- 製図
-


 製図は1年時に2単位(週2時間)。立体の表現方法や設計図の描き方を学ぶ授業です。1年生は、ドラフター(製図版)の使い方から、作図の練習、平面図学、投影図など、基礎から幅広く学習します。
製図は1年時に2単位(週2時間)。立体の表現方法や設計図の描き方を学ぶ授業です。1年生は、ドラフター(製図版)の使い方から、作図の練習、平面図学、投影図など、基礎から幅広く学習します。
2年生
- 実習
-


 2年生の実習は5単位(週5時間)。デザインの3つの分野(ビジュアルデザイン・プロダクトデザイン・エンバイロメントデザイン)について、作品制作を通じて実践的に学習していきます。2年生では、グループで意見を出し合ったり(グループワーク)、自分の考えや意見を人に伝える意見広告のデザイン、使う人のことを考えた製品のデザインなど、より実践的な課題に取り組みます。グループワークでは、小学生を対象としたワークショップの企画を考えます。対象が小学生なので、小学生が興味を持つような内容で、小学生が理解できるような説明と内容でなければいけません。各グループで話し合いをし、アイデアを出して、役割分担をしながら進めていきます。
2年生の実習は5単位(週5時間)。デザインの3つの分野(ビジュアルデザイン・プロダクトデザイン・エンバイロメントデザイン)について、作品制作を通じて実践的に学習していきます。2年生では、グループで意見を出し合ったり(グループワーク)、自分の考えや意見を人に伝える意見広告のデザイン、使う人のことを考えた製品のデザインなど、より実践的な課題に取り組みます。グループワークでは、小学生を対象としたワークショップの企画を考えます。対象が小学生なので、小学生が興味を持つような内容で、小学生が理解できるような説明と内容でなければいけません。各グループで話し合いをし、アイデアを出して、役割分担をしながら進めていきます。
- ビジュアルテクニック
-
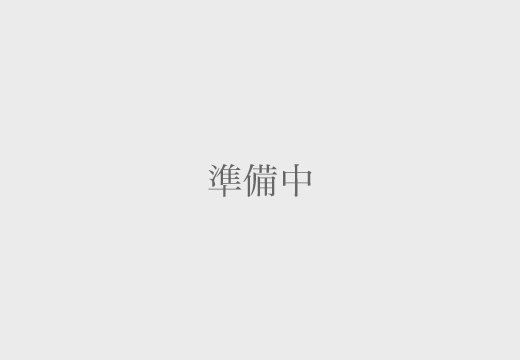
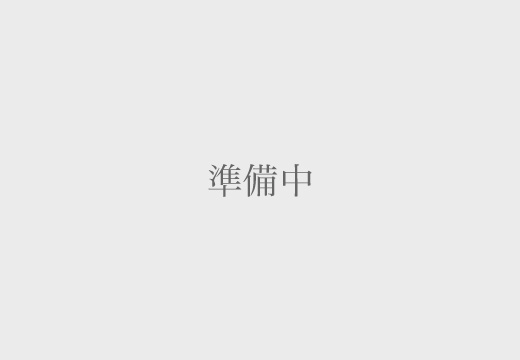
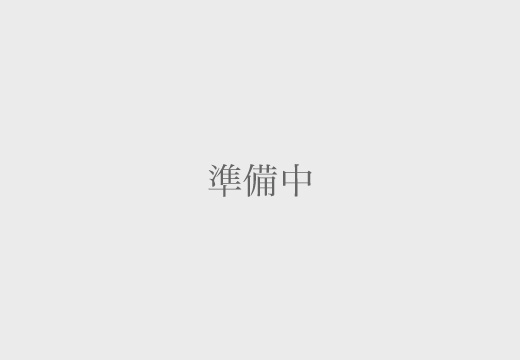 ビジュアルテクニックは“学校設定科目”といって岡工デザイン科独自の科目で、2年生で3単位(週3時間)です。様々な画材や技法を試す実験的な課題や、1年生の工業技術基礎で学んだシルクスクリーン印刷のより発展的な課題に取り組んだり、パソコンでIllustratorやPhotoshopなどの専門的なソフトを使ってより実践的なデジタル編集を学んだりしています。岡工デザイン科独自の科目なので、一定の到達目標や決まった枠組みが無く、授業内容は年々改良を重ねながら常に進化しています。
ビジュアルテクニックは“学校設定科目”といって岡工デザイン科独自の科目で、2年生で3単位(週3時間)です。様々な画材や技法を試す実験的な課題や、1年生の工業技術基礎で学んだシルクスクリーン印刷のより発展的な課題に取り組んだり、パソコンでIllustratorやPhotoshopなどの専門的なソフトを使ってより実践的なデジタル編集を学んだりしています。岡工デザイン科独自の科目なので、一定の到達目標や決まった枠組みが無く、授業内容は年々改良を重ねながら常に進化しています。
- デザイン実践
-
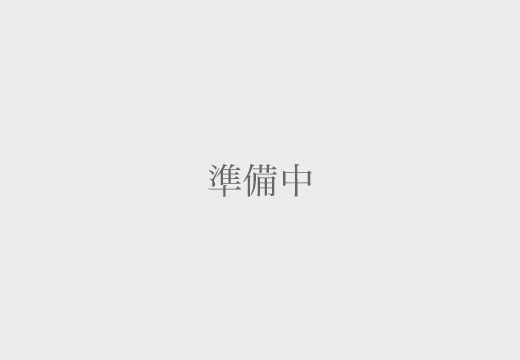
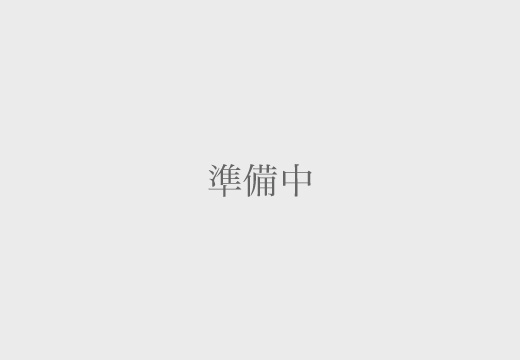
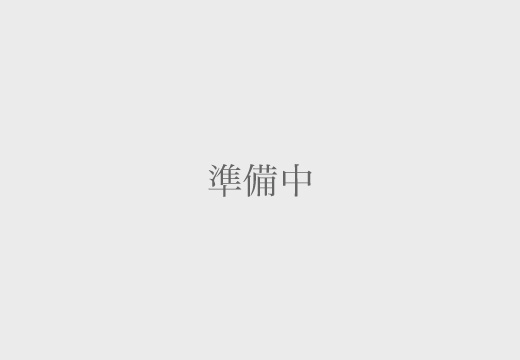 デザイン実践は2年時に2単位(週2時間)。デザインの専門用語や形態と構成の原理、材料や用具について、など、教科書に沿って半分座学、半分実習的な授業内容でデザインについてより理解を深め、専門知識を身につけていく科目です。
デザイン実践は2年時に2単位(週2時間)。デザインの専門用語や形態と構成の原理、材料や用具について、など、教科書に沿って半分座学、半分実習的な授業内容でデザインについてより理解を深め、専門知識を身につけていく科目です。
- 工業情報数理
- 工業情報数理は2年時で2単位(週2時間)。現在のような高度情報化社会の中で必要となるコンピュータにかかわる基本的な知識と技術を習得します。コンピュータの歴史と発達、情報化社会のモラルと管理、アプリケーションソフトウェアの基本的な使い方を学んでいきます。主にWindowsパソコンを使用し、Word・Excelなどのワープロ/表計算ソフトやPowerPoint等のプレゼンテーションソフトについても学習していきます。
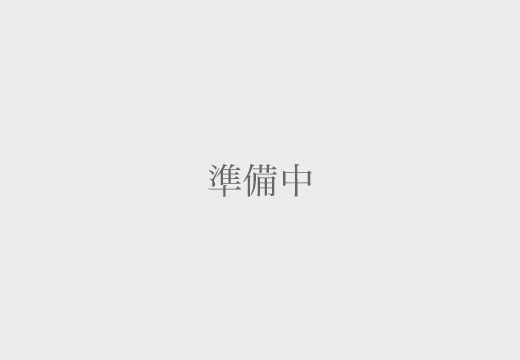
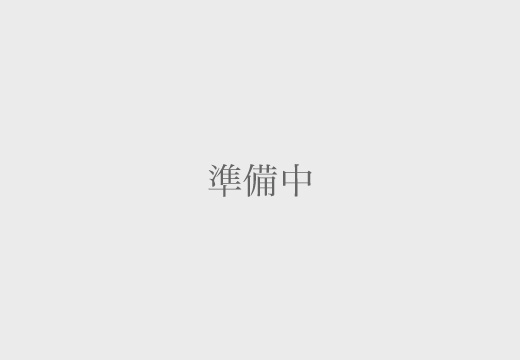
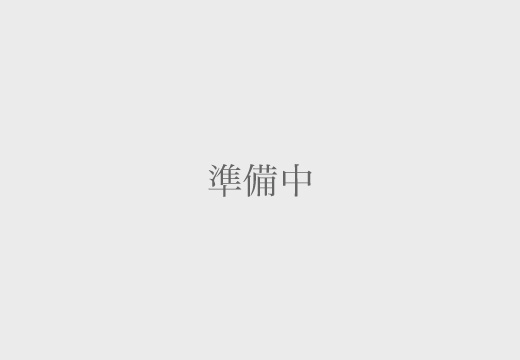
- 実習
-


 3年生の実習は2単位(週2時間)。デザインの3つの分野(ビジュアルデザイン・プロダクトデザイン・エンバイロメントデザイン)について、作品制作を通じて実践的に学習していきます。3年生の実習では、課題研究と絡めながらより専門的・実践的な作品制作に取り組みます。最近はパソコンで作品を制作したり提案をまとめたりすることが多くなっていますが、自分の頭で考え、それを形にしていく過程は昔から同じです。そしてAIが発達していく今後も変わることはありません。
3年生の実習は2単位(週2時間)。デザインの3つの分野(ビジュアルデザイン・プロダクトデザイン・エンバイロメントデザイン)について、作品制作を通じて実践的に学習していきます。3年生の実習では、課題研究と絡めながらより専門的・実践的な作品制作に取り組みます。最近はパソコンで作品を制作したり提案をまとめたりすることが多くなっていますが、自分の頭で考え、それを形にしていく過程は昔から同じです。そしてAIが発達していく今後も変わることはありません。
3年生
- デザイン実践
-


 デザイン実践は3年時に4単位(週4時間)。教科書に沿って半分座学、半分実習的な授業内容でデザインについてより理解を深め、専門知識を身につけていく科目です。
デザイン実践は3年時に4単位(週4時間)。教科書に沿って半分座学、半分実習的な授業内容でデザインについてより理解を深め、専門知識を身につけていく科目です。
- 課題研究
-


 課題研究は3単位(週3時間)。各自で研究テーマを設定し、1年間かけて作品を制作していきます。デザインサーベイ(調査)、資料収集をし、コンセプトを決めアイデアを出し、試作を繰り返して作品制作に入りますが、一人一人研究テーマが違うので、目標を定め、作業計画を立てながら進めていきます。完成した作品は、毎年1月に岡山県天神山文化プラザで開催している「卒業制作展」に展示をします。
課題研究は3単位(週3時間)。各自で研究テーマを設定し、1年間かけて作品を制作していきます。デザインサーベイ(調査)、資料収集をし、コンセプトを決めアイデアを出し、試作を繰り返して作品制作に入りますが、一人一人研究テーマが違うので、目標を定め、作業計画を立てながら進めていきます。完成した作品は、毎年1月に岡山県天神山文化プラザで開催している「卒業制作展」に展示をします。
- デザイン史
-


 3年時で2単位(週2時間)。日本と西洋の原始から中世、近代から現代までのデザインの歴史を学ぶ授業です。18世紀にイギリスで起こった産業革命以降、生産現場では工業化・機械化が進み、それに抗うようにウイリアム・モリスを中心に手工芸を見直すアーツ・アンド・クラフツ運動が起きます。20世紀初めには、近代デザインは機能主義、合理主義的な方向に向かっていきます。今、身の回りにある製品の起源や成り立ち、建築様式の変遷などを知ることで、改めてデザインについて興味が湧いてきます。
3年時で2単位(週2時間)。日本と西洋の原始から中世、近代から現代までのデザインの歴史を学ぶ授業です。18世紀にイギリスで起こった産業革命以降、生産現場では工業化・機械化が進み、それに抗うようにウイリアム・モリスを中心に手工芸を見直すアーツ・アンド・クラフツ運動が起きます。20世紀初めには、近代デザインは機能主義、合理主義的な方向に向かっていきます。今、身の回りにある製品の起源や成り立ち、建築様式の変遷などを知ることで、改めてデザインについて興味が湧いてきます。
- デザイン企画
-


 デザイン企画はデザインの3分野それぞれについて、現代社会との関わり、デザイン業務の進行、デザイン制作に関する著作権、意匠権など知的財産権について、作品制作を通じて総合的に学んでいきます。
デザイン企画はデザインの3分野それぞれについて、現代社会との関わり、デザイン業務の進行、デザイン制作に関する著作権、意匠権など知的財産権について、作品制作を通じて総合的に学んでいきます。