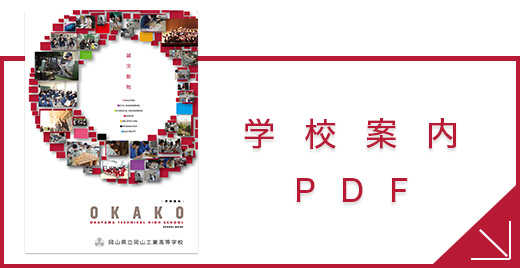歴史・沿革
1901年(明治34年)、岡山工業高校は生まれました。「誠実勤勉」の校訓の下、多くの若者が学び、巣立ち、社会のあらゆる分野で活躍してきました。
工業技術の習得と常にその先を探求する熱き若者の心が激動の明治・大正・昭和の時代を生き抜き、今日の社会を築きあげてきました。
そして今、工(たくみ)の伝統を守りつつ、新世紀の挑戦が始まっています。
ここには創造性を大切にする自由な校風、歴史と培われた知識と技術が息づいています。

- 1901年(明治34)
- 「岡山県立工業學校」創立。機械科・土木科・染織科(現在の化学工学科)の3科を設置。10月10日に文部省 (当時)より設立認可され、翌1902年10月10日に開校式を挙行。(これにより、岡工の創立記念日は10月10日となっています)
- 1914年(大正3年)
- 「岡山市立岡山工藝學校」創立
木工科・金工科・塗工科(現在のデザイン科)の3科を設置。
開校当時は岡山市船頭町の市立清輝橋小学校旧校舎を仮設としていたが、1926年(大正15年)岡山市東古松の新校舎に移転。 - 1944年(昭和19年)
- 岡山県第一工業学校(県立)と岡山市第一工業学校(市立)に校名変更。
- 1945年(昭和20年)
- 6月29日の岡山大空襲でB-29の焼夷弾により、県立校舎はほぼ全焼、市工は本館以外の実習等など6棟を焼失。
- 1946年(昭和21年)
- 岡山市第一工業学校に新たに建築科を設置
- 1949年(昭和24年)
- 県立と市立が統合され「岡山県立岡山西高等学校」に校名変更。
校舎は南方校舎と東古松校舎に分かれたまま。 - 1951年(昭和26年)
- 創立50周年
- 1952年(昭和27年)
- 校歌「東天燃ゆる」制定
- 1952年(昭和27年)
- 応用化学科を工業化学科に変更
- 1953年(昭和28年)
- 現在の「岡山県立岡山工業高等学校」に校名変更
- 1957年(昭和32年)
- 上伊福の県庁跡地(現在の岡工の場所)に校舎が統合移転することが決定し、1958年(昭和33年)2月に起工式が行われ、現在の1号館の建設開始
- 1959年(昭和34年)
- 南方校舎が伊福町校舎へ移転。新たに電気通信科を設置
- 1960年(昭和35年)
- 普通教室2号館が完成し、9月に東古松校舎が伊福町校舎に移転、2つの校舎に分かれていた岡工は伊福町校舎に統合完了。美術工芸科が改称され工業デザイン科に
- 1961年(昭和36年)
- 電気通信科が分割され、電子科と電気科に。これにより岡工設置は機械・土木・工業化学・工業デザイン・建築・電子・電気の7科となる。
- 1968年(昭和42年)
- 工業化学科募集停止化学工学科を新設。
- 1992年(平成4年)
- 工業デザイン科募集停止デザイン科を新設。
- 1993年(平成5年)
- 電子科募集停止情報技術科を新設。
- 2001年(平成13年)
- 創立100周年4月より年間を通して「100年祭」として様々な行事を開催。
- 2011年(平成23年)
- 創立110周年3年生を中心とした「110プロジェクト」で校内案内板や専門科棟配置図製作。
- 2014年(平成26年)
- 創立113周年 岡山工藝學校創立より100年
- 2016年(平成29年)
- 創立115周年
- 2021年(令和3年)
- 創立120周年
- 2024年(令和6年)
- 行幸啓 天皇皇后両陛下が本校を御視察